第3回目のオープンダイアローグ勉強会のテーマはリフレクティングでした。
前回までに、オープンダイアローグの成り立ちや目指すもの、基本原則を学んできて、今回は、どんなふうにオープンダイアローグセッションはすすめられていくのかの説明でした。
オープンダイアローグではリフレクティングを使って対話していきます。
その成り立ちは、セラピスト(観察者)がクライアント(観察されるもの)を見るという一方的な階層構造を取り除こうという試みで、2者間の会話は社会的いちづけにより一方的傾向の強いコミュニュケーションになりがちですが、リフレクティングを使うことで聴くことと話すことを分けて、内的対話に集中しながら、多様的表現できるようになるそうです。
リフレクティングのルールについて解説がありました。以下要約しました。
① その場の会話内容に基づいて、反応や解釈を行い、他の文脈から、持ち込まないこと。また、断定的な話し方は避ける
② 否定的なことを言わない。
③ 同室でチームが話す場合、リフレクティングチームメンバーが向き合って話すこと。これによって、聞いている人た ちを視線で縛ることなく、「聞かなくてもいい自由」を確保する。
④ 自分が話し手が何を話していたのを聞いたのか(特に印象に残った言葉や表現は、何か)、その言葉や表現からどんなイメージを思い 浮かべたのか、それらの言葉やイメージは、自分にとってはどんな感じがするのか、そこでどんなアイデアを考えることができたのか。
唯一の「正解」や「真理」が存在し、誰かがそれを有しているという考え方(「あれか、これか」)か ら、物事にはいろいろな見方があり、様々な意見の交換から、更に、新たな会話が展開していくこ とが望ましいとする考え方(「あれも、これも」)への転換の姿勢 (リフレクティング 矢原 隆行著)
具体的なリフレクティングの方法を図解で解説頂き、講義は終了しました。
ワークは、オーブンダイアローグのデモを見学
代表者が台本を使い、モデルケースを朗読しました。
見学者には、登場人物の中から1人えらんで、その人になったつもりになって見学し、感じてもらい、デモ終了後に感じたことなどを話しあいました。
台本はこちらからアクセスできます。
シナリオ1です。
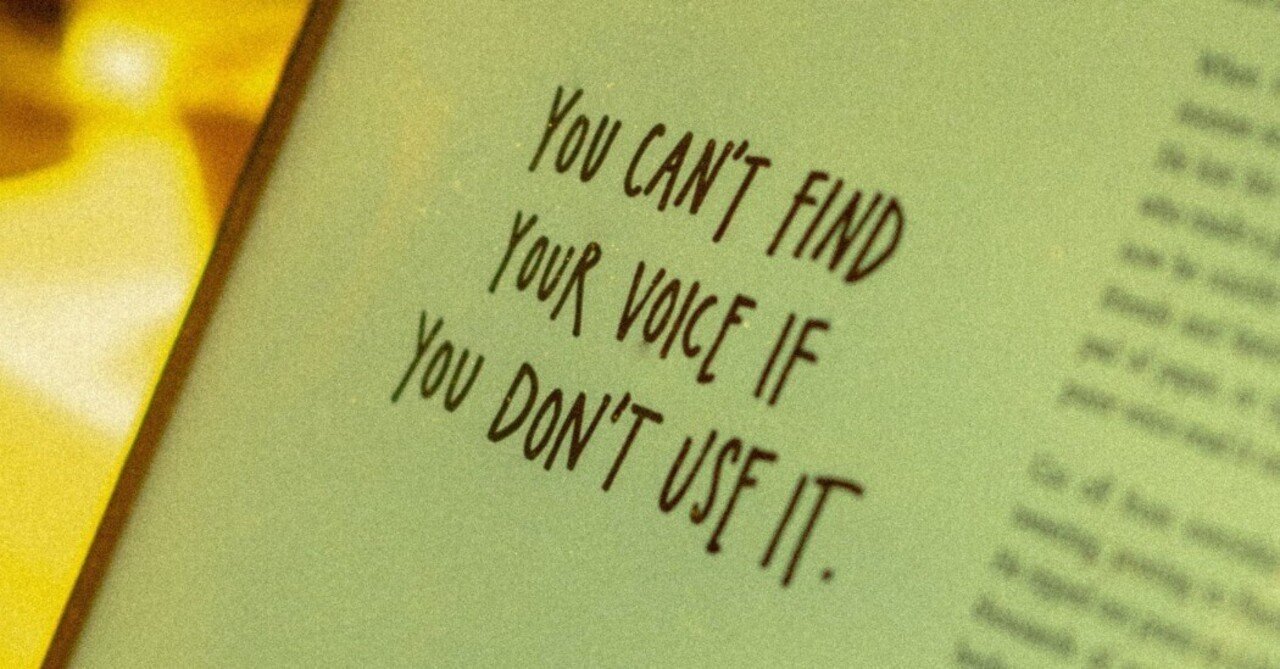
参加しての学び
今回は、オープンダイアローグをするにあたり、具体的にどうするのか学びました。私が今まで経験してきた、結論を求める話し合いと、感覚が大きく違うなと感じました。
特に自分が話し手が何を話していたのを聞いたのか(特に印象に残った言葉や表現は、何か)、その言葉や表現からどんなイメージを思い 浮かべたのか、それらの言葉やイメージは、自分にとってはどんな感じがするのか、そこでどんなアイデアを考えることができたのか。
という部分です。
自分の内的対話を置いていく感覚というのがいままでにあまりない経験で練習を必要とするなと感じました。
また、台本を使ったワークでは、ファシリテーターのリフレクティングのルールにのっとった言葉遣いや話の切り分けのおかげで、その場に対立を生むのではなく、その場に集まった人それぞれが、話を聞いてもらった感覚をもったと感じました。、リフレクティングのルールを使いこなせるようになることで、日常生活でも余計な対立をさけられるかもしれないなと思いました。勉強会を日常生活にも役立てるために、練習していきたいです。





コメント